丂偝偰師偵丄椺擭偙偺帪婜偵侾擭揰専傪幚巤偟偰偄傞偺偱丄崱擭傕幚巤偟偰偄傑偡丅壓夞傝偼帪娫偺娭學偱傑偩尒傟偰側偄偺偱偡偑丄崱偺偲偙傠丄埲壓偺俁揰偺晄嬶崌傪敪尒丒廋棟偟傑偟偨丅
侾丂彆庤惾懁傾僢僷傾乕儉僔乕儖岎姺
丂埲慜ML偺儊儞僶乕偵嫵偊偰傕傜偭偨曽朄偱僩儔僀偟丄姰帏側巇忋偑傝偵側傝傑偟偨丅億僀儞僩偼師偺俀揰偱偡丅
(侾)丂傾僢僷傾乕儉傪僋儘僗儊儞僶偐傜奜偟偰嶌嬈偡傞偙偲乮儘傾傾乕儉傪壓偐傜僕儍僢僉偱巟偊偰偍偗偽丄儃乕儖僕儑僀儞僩偼奜偝側偔偰OK偱偡乯
(俀)丂傾僢僷傾乕儉僺儞偺恀傫拞偺嵶偄晹暘偱丄弖娫愙拝嵻傪巊偭偰敿妱傝偵偟偰偍偄偨僔乕儖傪尦捠傝偵愙拝偟丄愙拝嵻偑屌傑偭偨傜丄僔乕儖傪杮棃偺埵抲傊偢傜偡偙偲丂弖娫愙拝嵻偼傾儘儞傾儖僼傽偺崌惉僑儉梡傪巊偄傑偟偨丅塼忬偵偟偨偺偱偡偑丄僛儕乕忬偼屌傑傞傑偱彮偟帪娫偑偐偐傞傛偆偱偟偨偺偱丄塼忬偱惓夝偱偟偨丅
-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-丒-
亂俥僒僗傾乕儉俷/俫亃
丒僼儘儞僩傾乕儉慻傒晅偗乮擄堈搙丗仛仛仛仚仚乯丅
1) 怴偟偔側偭偨僼儘儞僩傾乕儉

丂儘傾傾乕儉偺埵抲傪僕儍僢僉傪巊偭偰崌傢偣傞偺偑帪娫偑妡偐偭偨丅
丂偽傜偟側偑傜儃乕儖僄儞僪偺僈僞傪傒偨丅備傞偄偺偼偁傞偑僈僞偼側偄丅
丂埲慜岎姺偟偨僋儘僗儘僢僪偵傕僈僞偼側偐偭偨丅
丂屵屻5帪傪夁偓偰埫偔側偭偨偙傠丄嵟屻偵杮掲傔傪偟偰偄偨傜丄僕儍僢僉傪妡偗傞応強偑埆偔奜傟丄儃僨傿傪墯傑偟偰偟傑偆丅儃僨傿偑墯傫偱墯傒傑偟偨丅偦傫側懯僕儍儗傕堦斣徫偊側偄偺偼帺暘偱偟偨丅
丂岎姺屻偺僀儞僾儗丅
丂楬柺偐傜偺徴寕偑擃傜偐偔側傝丄忔傝怱抧偑椙偔側傝傑偟偨丅姶偠偱偄偆偲丄僑儞僑儞偐傜丄僪儞僪儞偱偟傚偆偐丅岎姺慜偺傾乕儉偼丄彆庤惾懁傾僢僷偼僗僇僗僇丄塣揮惾懁儘傾偼僑儉晹偵婽楐偲偄偆姶偠偱楎壔偑柧傜偐偱偟偨偺偱丄偍偦傜偔偦偺奺晹偱徴寕偑媧廂偝傟傞傛偆偵側傝丄塣揮幰偵揱傢傞徴寕偑尭偭偨偺偱偟傚偆丅
丂楬柺偺偆偹傝偵懳偡傞僞僀儎偺捛廬惈偑椙偔側偭偨傛偆偵姶偠傑偡丅
丂僔儉偺悢偝偊娫堘偊側偗傟偽堄奜偵傾儔僀儊儞僩偼曵傟側偄偱丄僴儞僪儕儞僌偵偼偦傟傎偳堘榓姶偼偁傝傑偣傫丅偱傕嬤偔傾儔僀儊儞僩傪庢傝捈偡梊掕偱偡丅
丂傑偨僗僥傾儕儞僌廃傝偺僌儕僗傾僢僾偲E/g僆僀儖偺岎姺丄僨僼僆僀儖偺岎姺傪梊掕偟偰偄傑偡丅
丒儘傾傾乕儉慻棫丅
1) 偱偒傑偟偨丅懌夞傝偺僑儉晹昳偼丄嬥懏晹偺懴梡擭悢偐傜偡傞偲尩偟偄忬嫷偵偁傞偲尵偊傑偡丅僔儕僐儞僌儕乕僗側偳偱晛抜偐傜戝帠偵偟偰傗傞偙偲偑娞怱偐傕丅
偁偲傾僢僷乕傾乕儉丄僌儕乕僗擖傝偡偓丅

丂庤弴偼
丂1.丂儘傾傾乕儉偵屻僽僢僔儏傪埑擖丅
丂2.丂僼儖僋儔儉僺儞偵僨傿僗僞儞僗儚僢僔儍傪慻傒晅偗丄儘傾傾乕儉偵僙僢僩偡傞丅
丂3.丂儘傾傾乕儉偵慜僽僢僔儏傪埑擖偡傞丅
偱偡丅
丂崱夞偍偒偨栤戣偼丄擇偮丅
丂堦偮偼丄崱夞傾乕儉丄僺儞偲傕偵暡懱揾憰偟偨偑丄偦傟傪岆偭偰丄僽僢僔儏傪憓擖偡傞晹暘偵傕埶棅偟偰偟傑偭偨偨傔丄僽僢僔儏丄儚僢僔儍偺擖傝偑埆偔側偭偰偟傑偭偨偙偲丅
丂擇偮栚丄庤弴3偱丄慜僽僢僔儏傪憓擖偡傞偲偒丄僾儗僗偺榞偑幾杺偵側偭偰丄忋庤偔僙僢僩偱偒側偐偭偨丅
丂夝寛朄偼丄1偵偮偄偰偼僆僀儖傪揾偭偰偹偠崬傫偩丅偙傟偼偁傑傝椙偔側偄偑丄揾憰傪攳偑偡偺偼柺搢側偺偱偡丅
丂2偼丄10cm偖傜偄搚戜傪偐偝忋偘偟偰傗傟偽僙僢僩偱偒偨偺偱丄嬤偔偵偁偭偨栘曅傪壓偵晘偄偰埑擖嶌嬈丅偨偩搚戜偵栘側偺偱堦搙埑擖偡傞偲墯傒偑偱偒偰巊偊側偔側傞偙偲偵拲堄丅
丂墯傒偑偱偒傞偩偗側偺偱乮嵽幙偵傛偭偰堘偄偼偁傞乯丄岦偒傪曄偊傟偽壗夞偐偼巊偊傞丅
丂偙傟偱傾乕儉慻棫偰偼廔傢傝丅
丂幚嵺嶌嬈偟偰傒偰偩偑丄偙傟傪偡傋偰埶棅偟偰100倠偼僴僢僉儕尵偭偰埨偄丅崱偱傕埶棅庴偗偰偔傟傞偺偐側乣丄嶳拞帺仜幵丄堦夞偟偐峴偭偨偙偲側偄偗偳丅
丒傾僢僷傾乕儉慻棫丅
1) SST丅栘惢偺戜偲僶僀僗乮奃怓偺晹暘乯丄僾乕儔乕乮塃偺崟偄暔懱乯傪慻傒崌傢偣偰傑偡丅戜傕僶僀僗傕偡偖夡傟傞乮妱傟傞乯偺偱丄悢搙巊梡偟偰偼傑偨巊偄曽傪岺晇偟偰偲丄偙偺晹暘偺嶌嬈偼昗弨壔偱偒傑偣傫偱偟偨丅妝側曽朄偑偁傟偽偳側偨偐嫵偊偰偔偩偝偄丅
2) 崟岝傝偡傞傾僢僷乕傾乕儉丅


丂傾僢僷傾乕儉偺慻棫偼傑偢丄傾乕儉傪172mm嫮偵奼戝偟丄偦偺忋偱僼儖僋儔儉僺儞傪僙僢僩偟僱僕僽僢僔儏傪偹偠崬傓偲偁傞丅偦偺奼戝暘偑僱僕僽僢僔儏傪僼儖僋儔儉僺儞偵墴偟晅偗傞椡乮僾儗儘乕僪丄梊晧壸乯偲側傞偺偱丄偙傟偼婯掕抣偳偍傝偵偟側偄偲僈僞偲側偭偰昞傟傞壜擻惈偑偁傞丅
丂偲偙傠偱惍旛彂偱偼丄傾乕儉偺偳偙偑172mm偵側傟偽偄偄偐崱傂偲偮偼偭偒傝偟側偄丅偄偡乁偵暦偔傕傗偼傝偼偭偒傝偲偼傢偐傜側偄傛偆偩偭偨丅
丂偟偐偟懡偔偺恖偑僽僢僔儏寠偺弌偭挘傝偺撪懁偩傠偆偲偄偆偙偲側偺偱丄偦偙傪婎弨偵峫偊傞偲丄偦偺晹暘偼160mm傎偳丅12mm奼戝偡傟偽傛偄丅
丂杮棃偼SST偲偟偰僄僉僗僷儞僟側傞傕偺乮捾晅偒僱僕僕儍僢僉乯偱丄傾乕儉傪奼戝偡傞偺偩偑丄摉慠偦傫側傕偺偼側偄丅
丂偦傟偱帺暘偱SST傪嶌偭偨偺偩偑丄傗偼傝婛惢昳偺棳梡偱偼尷奅偑偁傞傛偆偱乮扨偵壛岺偑愘偄偩偗偐乯慻傒崌傢偣偨晹昳偑寢峔夡傟傞丅栘惢偺戜偼妱傟丄捾戙傢傝偺僶僀僗傕妱傟偨丅
丂偟偐偟丄偲傝偁偊偢強掕偺僒僀僘偵奼戝偱偒傞傛偆偵側偭偰婥偯偄偨偺偼丄僽僢僔儏寠偑斀傝偡偓偰偄傞乮暯峴偵峀偑傜側偄乯偲偄偆偙偲丅偍偦傜偔捾偺晹暘偑僽僢僔儏寠偺奜廃偺墱傑偱側偗傟偽丄擇偮偁傞僽僢僔儏寠偑暯峴偵側傞傛偆偵奼戝偱偒側偄偺偩傠偆丅偲傝偁偊偢帺暘偵偦傫側壛岺媄弍偼側偄偟丄捾晹暘偺崉惈偼憡摉昁梫偲偍傕傢傟傞偺偱帺嶌偼晄壜擻偲敾抐丅偦傟偵幚尡偵偟傛偆偟偨傾乕儉偼奼戝偟偨傑傑栠傜側偔側偭偨乮165mm偖傜偄乯偺偱丄傕偟12mm奼戝偱偒傞偲偟偰丄偦傟偼偐側傝恦懍偵嶌嬈偟側偗傟偽傾乕儉偼曄宍偟偰偟傑偆偩傠偆丅
丂側偺偱偹偠崬傔傞掱搙偵奼戝偟偰乮165mm掱搙乯慻棫偰丅偙傟偱傕帺暘偺榬椡掱搙偱偼傃偔偲傕偟側偄偺偱丄偄偒側傝僈僞偑偱偰崲傞偲偄偆傛偆側偙偲偼側偄偩傠偆丅
丒儘傾傾乕儉暘夝丅
1) 傾乕儉晹昳丅
2) 僺儞偺嵶偄傎偆偐傜僽僢僔儏偼敳偒傑偡丅
3) 杮摉偼僽僢僔儏偲僺儞偺娫偵偼僨傿僗僞儞僗儚僢僔儍乮偩偭偨偐側乯偑擖偭偰偄傑偡丅偦傟偑僽僢僔儏偺墢傪嬒堦偵墴偟傑偡丅
4) 僽僢僔儏偑敳偗偨傜僺儞偑敳偗傑偡丅
5) 傕偆曅曽偼揔摉偵敳偄偰偔偩偝偄丅
6) 埲壓僀儗僊儏儔乕側応崌丅僽僢僔儏偼奜懁偵嬥懏惢偺墢偑偮偄偰傑偡丅
7) 撪仺奜偐傜敳偗側偄応崌丄偙偺傛偆偵墢傪棊偲偟偰奜仺撪傊敳偒傑偡丅
8) 僽僢僔儏偺奜墢傪棊偲偡偲偒偼傾乕儉杮懱偺柺傪戝愗偵嶍傝傑偟傚偆丅
9) 奜仺撪偵敳偔応崌丄僺儞偑幾杺偵側傞応崌傕偁傞偐偲巚偄傑偡丅偦偺応崌偼丄僽僢僔儏偺撪懁傪棊偲偣偽懡彮僋儕傾儔儞僗偑偱偒傑偡丅偦傟偱傕懯栚側傜僺儞偺傎偆傪壗偲偐偡傞傛傝側偄偱偟傚偆丅
10) 偙傫側姶偠偺嬥懏偺搚戜傪嶌惉偟傑偡丅墯傒晹偼儘傾傾乕儉偺傊傝傪旔偗傞偨傔丄廲偺嬻敀晹偼僼儖僋儔儉僺儞傪旔偗偰撪懁偐傜傾乕儉傪巟偊傞帪偵昁梫偱偡丅
11) 偙傟偼姰惉屻偱偡偑丄偙偺晹暘傪僺儞偺偁傞忬懺偱巟偊傞昁梫偑偁傞傢偗偱偡丅姰惉屻偵幨恀偱尒偊傞嬥怓偺晹暘傪壖掲傔偟傑偡丅杮掲傔偼庢傝晅偗忬懺偱峴偄傑偡丅









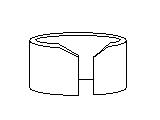

丂傑偢杮棃偺庤弴偲偟偰偼丄嵍塃偺僫僢僩側偳傪奜偟偨屻丄僾儗僗偵偰曅曽偺僽僢僔儏傪敳偒丄僼儖僋儔儉僺儞傪敳偄偨屻丄傕偆曅曽偺僽僢僔儏傪敳偔丅偙偺帪丄僽僢僔儏偺墢偵偆傑偔椡偑寽偐傞傛偆偵SST乮傾乕儉偺搚戜丄僼儖僋儔儉僺儞偺僒億乕僩乯傪巊梡偡傞丅
丂僽僢僔儏偼撪懁偐傜偟偐敳偗側偄憿傝偵側偭偰偄傞偺偱丄僽僢僔儏偼婎杮揑偵僼儖僋儔儉僺儞傪夘偟偰墴偡偙偲偵側傞丅
丂幚嵺偵偼SST側偳側偄偺偱丄儘傾傾乕儉偺偦傝傪旔偗傞宍偺搚戜傪嶌傞偲偙傠偐傜僗僞乕僩偡傞丅傾乕儉傪僾儗僗偵偐偗傞偵偼昁梫側嶌嬈丅嬥懏摏傪僌儔僀儞僟乕偱嶍傞丅
丂傾乕儉偺忬懺偑傛偗傟偽忋偱嶌惉偟偨戜偵儘傾傾乕儉傪忔偣丄僽僢僔儏傪椉曽敳偗偽傛偄丅惍旛彂偱偼僼儖僋儔儉僺儞偵僨傿僗僞儞僗僠儏乕僽側傞傕偺乮SST乯傪旐偣傞偙偲偵側偭偰偄傞偑丄柍偔偰傕偄偗側偄偙偲偼柍偄乮僺儞偑嬋偑傞壜擻惈偼崅偄乯丅曅曽偼帺暘傕偁偭偝傝偲奜傟偨丅
丂偟偐偟傕偆堦曽偼丄偼偠傔偺僼儖僋儔儉僺儞傪墴偟偨嵺偵僽僢僔儏偺墢偑捵傟偨乮捵傟偰偄偨丠乯偺偲丄僗儁乕僒乕偲偟偰偺儚僢僔儍偑曄宍偟偨偨傔偆傑偔僽僢僔儏偑敳偗偢丄帋峴嶖岆偺偺偪乮僽僢僔儏撪懁偺嬥懏晹暘傪墴偟弌偟丄僼儖僋儔儉僺儞傪敿暘敳偄偨偺偪乯丄嵟廔揑偵偼僽僢僔儏偺奜墢傪棊偲偟丄撪懁偵敳偄偨丅
丂寢嬊偺偲偙傠丄側偤墢傪棊偲偟偰丄奜仺撪偵敳偄偨傎偆偑椙偄偐偲偄偆偲丄撪仺奜偩偲偳偆偟偰傕娫偵挿偄僗儁乕僒乕乮僼儖僋儔儉僺儞O倰僨傿僗僞儞僗僠儏乕僽O倰揝僷僀僾乯傪夘偝偞傞傪摼偢丄偦傟偑僽僢僔儏傪恀偭捈偖墴偝側偄乮悅捈偑弌偵偔偔丄椡偑摝偘傞乯偐傜偩偲巚傢傟傞丅
丂側偺偱偙傟偐傜傕偟嶌嬈偝傟傞曽偱SST偑側偄応崌偼丄
嘆傑偢傾乕儉傪巟偊傞搚戜傪嶌傞丅嬥懏摏偵儘傾傾乕儉偺偦傝偑摉偨傞晹暘傪嶍傞丅
嘇傑偢偼僺儞偱偦偺傑傑墴偟偰傒傞丅偙偺偲偒僼儖僋儔儉僺儞乮埲壓僺儞乯偺悅捈搙偼擖擮偵僠僃僢僋丅
嘊僽僢僔儏偑敳偗傟偽僺儞偼敳偗傞偺偱丄傕偆曅曽偺僽僢僔儏偼揔摉偵僽僢僔儏偺宎傪墴偣傞嬥懏拰傪慻傒崌傢偣丄僾儗僗偵偰墴偟弌偡丅
嘋嘇偱僽僢僔儏偺墢側偳偑曵夡偟偨傜偛廌彎條丅嘊偱僺儞偑嬋偑偭偨応崌傕摨條偱偡丅
丂僽僢僔儏偺墢偑曵夡偟偨応崌偼丄傑偢僗儁乕僒乕儚僢僔儍偲僽僢僔儏偺撪懁嬥懏曅傪僺儞偵偰墴偟弌偟傑偡乮偲偄偆傛傝僺儞傪奜懁偵摝偑偡丄摝偘側偗傟偽丄傗傗奜偟婥枴偵偟偰丄僾儗僗偺搚戜偑僺儞傪摝偘傞傛偆偵壛岺偡傞乯丅師偵斀懳懁偺僽僢僔儏偺奜墢傪棊偲偟丄撪懁偵僽僢僔儏傪敳偒丄敳偗偨傜斀懳傕摨條偵偡傟偽丄僽僢僔儏偼偡傋偰庢傝彍偗傑偡丅
丂嘊偼僺儞傪廋惓偟丄僺儞埲奜偺嬥懏拰偱帋偟偰傒傟偽傛偄偱偟傚偆丅
丂偄偮傕偍悽榖偵側偭偰偄傞儗儞僞儖僈儗乕僕偺JOY偩偑丄崱夞偼擄堈搙偑崅偐偭偨傛偆偱憡摉搙丄庤揱偭偰偄偨偩偄偨乮僽僢僔儏偺墢棊偟側偳乯丅
丂堦擔偍悽榖偵側偭偰仐10k丅偁偺嶌嬈偵偙偺抣抜偼怽偟栿側偄偖傜偄埨偄丅JOY偺幮挿傕丄彜攧偱丄抦偭偰偨傜愨懳惪偗晧傢側偄嶌嬈偲偺偙偲偱丄帺暘傕嶌嬈拞丄壗搙傕掹傔偐偗偨乮僽僢僔儏偑曄宍偟偨偲偒丄僺儞偑嬋偑偭偨偲偒乯丅埲慜偦偺嬝偺僔儑僢僾偵暦偄偨偲偒仐100k偲尵偭偰偄偨偺傕丄幚嵺偦偺嶌嬈傪傗偭偰傒傟偽丄埨偄婥偡傜偟傑偟偨丅偲偵偐偔晅偒崌偭偰偔傟偨幮挿偵偼姶幱丅
丂偙偺嶌嬈偼僾儗僗丄僌儔僀儞僟丄枩椡丄嬥懏摏奺庬乮搚戜偺傕偲丄僽僢僔儏傪墴偡偪傚偆偳椙偄捈宎偺嬥懏曅丄僜働僢僩偺僐儅側偳偱傕壜乯偑昁梫偱丄嬥懏壛岺偱偼婍梡偝傕昁梫側偺偱丄偐側傝晘嫃偼崅偄偐傕偟傟傑偣傫丅